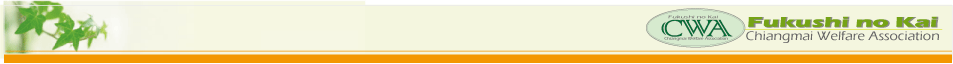 |
|||
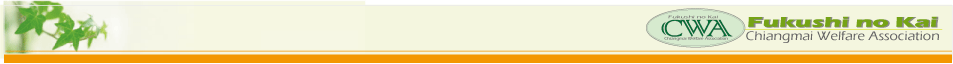 |
|||
| <気になるニュース・話題> (山口等) | |
| ネットに氾濫している様々な情報の中から、これは面白いという話題を、拾い集めて紹介してまいります。 | |
|
タイ在留邦人事情 絶えぬ「困窮邦人」 newsclip.be 2015.08.23
年間1700万人以上の日本人が海外旅行に出る昨今、日本人が巻き込まれる事件、災害、犯罪が
在外公館が援護した困窮邦人は2013年、全世界で383件(前年395件)に達し、うちアジアが 「アジアで困窮」と聞くと、バックパッカーの成れの果て、浮浪者同然といった身なりを想像しがちだが、 前述の「海外邦人援護統計」を見ると、性別・年齢別では、圧倒的に男性が多く 20-29歳、60-69歳に集中している。困窮に陥る理由は、「無計画な行動で所持金を 使い果たす」ことが第一に挙げられるが、不慮の事故・病気による入院・通院で負債 を抱え込む場合もあり、タイではひんぱんに見受けられるという。
ロングステイに十分な蓄えを用意しながらも、数年で使い果たした事例もある。
困窮邦人の援護は、「それじゃ、明日の飛行機で帰りなさい」で済むように思えるが、そんな簡単な 困窮と判断すれば、それに至った経緯を聞き、資金的援助が可能な身内や知人が日本に存在するかを 大使館関係者は、「その国の法令を遵守し、堅実な滞在を心がけてほしい」と話す。
好き好んで困窮する者はいない。自身のみならず、周囲に心配な同胞がいるときは、
|
|
|
|
|
|
なぜ、医者は自分では受けない治療を施すのか 緩和ケア診療所「いっぽ」医師 萬田緑平 月刊プレジデント 2015.05.05 配信 医者は自分では絶対に避けるような多大な困難をともなう治療を患者に施術することがある。 医者も人間ですから、必ず病気になります。当然、がんに罹る可能性もあります。 しかし多くの医者は、自分が病気になったとき「やらないほうがいい治療法」があること、
平たく言えば、自分と自分の身内には、すすめられない治療がある。しかし患者さんに施している
病気を治す、というのが医者の当然の役目ですから、全知全能全人格を使って治療することが前提です。 医療報酬やら薬の投与点数やら手術の実績やら、病院や医師が利益を得るような構造上の問題も 医者が患者さんに治療法を説明するとき、“エビデンス”という言葉を使います。
(中略) (中略) つらい例を挙げますが、「もう、こんなつらい治療はたくさんだ。家に帰りたい」と暴れるからベッドに
しかし、家族も納得して、患者さん本人も苦痛ばかりで治療を終わらせて家に帰りたいと思っているのに、 「治療を続ければ亡くならないのですか?あと何日命が延びるのですか?本人やご家族は退院を
 |
|
|
|
|
|
「長生き本当に幸せか」問う筆者・・ 執念消えぬ80代ストーカー78歳AV女優、高齢者の性と犯罪 80歳のストーカーから78歳のAV女優まで、ノンフィクション作家の新郷(しんごう)由紀さん(47)が 取材対象には、78歳になっても「現場の雰囲気が好きなの」と意欲を示す古希熟女市場で 高齢者の取材を始めた新郷さんはAV業界の「JK市場」、すなわち熟年高齢者市場が活性化
取材を続ける中で自身も複数の高齢者ストーカーから被害に遭い、
|
|
| |
|
|
|
|
|
老人ホーム”化する暴力団の実情とは・・・ 組員全員「年金受給者」層!?
たとえ老人ばかりでも、組員がいるだけでもまだマシ---これが暴力団の現状。 日本社会が少子高齢化すればヤクザ社会が高齢化するのも必然なのだが、その実態は すぐ近くに「おばちゃんの原宿」と呼ばれる巣鴨地蔵通り商店街があったので、ひどく印象に残った。 幹部たちを紹介されたが、すべて組長より年上の「若い衆」だ。よくみると事務所内に 「会社に勤めるような感覚で、給料が欲しいとか休みをよこせとか言いやがる。 日本全体が少子高齢化なのだから、暴力団だって高齢化するのは当然ではある。が、
「いまじゃ組のために懲役に行っても、家族の面倒すら見てもらえない。
もはや暴力団対策は、警察のシノギと表現するのが、もっとも正確かもしれない。 |
|
|
|
|
|
何でも効く 驚異の「腸内フローラ」・・・前月号の続編
糖尿病 糖尿病は、血糖値を調整するインシュリンが膵臓から分泌されにくくなる病気だ。
腸内フローラは、精神的な疾患との関係も知られている。 カナダのマクマスター大学医学部のプレミシル・ベルチック氏は、活動が活発で好奇心が旺盛なマウスと、 「臆病で優柔不断だったマウスが、突然大胆で活動的になりました。台から降りるのも素早くなった。 遺伝的に自閉症を持っているマウスの腸内フローラを変えることで、症状が軽減したと 「我々は、うつ病患者に腸内環境に良い影響を及ぼす腸内細菌を投与することで、不安やうつが改善するという結果も
腸には、脳に次いで大きな神経ネットワークがある。「腸は第二の脳」と言われる所以だ。 脳でストレスや緊張を感じるとお腹を壊すことがあるように、脳が腸に与える影響は以前から知られていたが、 身体全体の不調も、頭の働きや性格も、すべて腸内フローラが握っている これまでの常識を覆すこの事実が、 くれば、腸内フローラをコントロールするだけで病気を治すことができるようになる。 それだけではない。将来的には「病気にならない体」を作ることだって可能となるだろう。 辨野氏が言う。 「腸内フローラを調べて『あなたはこの菌が多いから、この病気になるリスクが高まっている』ということを 終わり |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第11回 | |
| 品格のない老人が増加? 「元気な子産めないわよ」と妊婦を立たせ優先席座った高齢者
かって、眉をひそめるのは老人が若者に対して、と相場は決まっていたが、最近の我が国では若者が老人に眉をひそめるケースが増えている。公共の場が「老人vs若者」で一触即発になったケースもある。10代の女子大生はこんな体験をした。 「大きなお腹の妊婦さんが優先席に座っていたのですが、そこにあとから乗ってきたおばあさん『臨月近いんでしょ、座ってたらお産が重くなるよ』と声をかけたんです。妊婦さんは『立ってると辛いんで・・・』と応えたのですが、『そんなんじゃ元気な子を産めないわよ!』と一喝。結局自分が座ってしまいました」 この女子大生は自分が座っていた席を妊婦に譲り、高齢女性に対して「自分が座りたかっただけじゃないですか」と噛みついた。すると隣の関係のない高齢男性から「お年寄りその言い方はなんだ!」と横槍が入り、別のサラリーマン風男性が「いや、この子がいっていることは間違っていない」と返して車内が緊迫した雰囲気になったという。 社会学者で甲南大学准教授の安部真大氏はこう指摘する。 |
|
| 「戦後の厳しい時代をくぐりぬけてきた世代と、今の若い人とは価値観が違って当然。『私が妊婦だったときはこうだった』 『自分はお年寄りを大切にしてきた』という思いがあるから、シニアが若い人とコミュニケーションをとると、そのギャップに ストレスを感じることになる。それがいわば被害者意識を増大させ、『弱い立場なんだから、ちょっとくらいいいじゃないか』 『先輩のいうことは聞くべき』という感情になって、品格を欠いた発言をしてしまうのでしょう」 |
|
| 第十回 | |
| 社会保障・税番号制度(マイナンバー)の実施間近に! | |
私たちがあまり関心を持たないうちに、マイナンバー制導入の日が間近にせまってきました。昨年2014年10月にはマイナンバーのコールセンターが開設されました。 今後のマイナンバー制導入実施の概略をごく簡単に紹介します。 .jpg)  .jpg) 1、今年2015年10月以降、マイナンバーが記載された通知カード(紙製)が市区町村から住民票のある住所に郵送される。 2、2016年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になる。 ※民間事業者(金融機関)も税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱う。 3、個人番号カード(ICチップ付き)の取得は、2016年1月以降市区町村に申請。取得は義務付けられていない。 4、国外に居住など住民票がない場合は、マイナンバーは指定されない。 詳細は下記をクリックして確認してください。 内閣官房ホームページ |
|
| 第九回 | |
| 年金受給開始年齢が65歳から70歳に引き上げなら1000万円減に 週刊ポスト2014年10月31日号 | |
いよいよ年金官僚の悲願である「受給開始年齢」の再引き上げ計画が本格的に動き出した。10月10日、政府の社会保障制度改革推進会議で、清家篤議長が現在65歳の受給開始年齢について「引き上げることもありえる」と宣言した。   振り返れば「60歳→65歳」に引き上げられたのは2000年の制度改正時。2004年には、小泉政権が「これで年金制度は100年安心」といって、受給額2割カットと保険料3割アップをゴリ押しした。 そして今回の受給開始年齢の再引き上げ計画である。100年どころか、たった10年しかたっていない。「年金博士」として知られる社会保険労務士の北村庄吾氏はこう指摘する。 「政府は2019年に行なわれる財政検証までに67〜68歳に引き上げることを画策しています。あわよくば70歳までの引き上げを狙っている。その布石はすでに打たれています」 1つ目の布石は、2012年に成立した改正高年齢者雇用安定法だ。これにより、企業が65歳までの雇用を義務付けられた。過去、定年が55歳から60歳に引き上げられた際にも、受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられた。65歳定年制は70歳受給開始へのステップといっていい。 2つ目は、今年5月、田村憲久・前厚労相が受給開始を本人が希望すれば75歳まで繰り下げられる仕組みを検討すると表明したことだ。 現行制度では受給開始を65歳から1か月遅らせる(繰り下げる)ごとに年金額が0.7%増える。ただし、繰り下げは70歳までしか認めていない。75歳まで繰り下げを可能にすることは、受給開始年齢引き上げのための地ならしと見られる。 仮に「65歳→70歳」が実現すれば、厚生年金加入者の場合1人当たりざっと1000万円のカットとなる。 |
|
| 第八回 | |
| さまよう墓石,不法投棄続々 2014.07.30 朝日新聞デジタル | |
| 先祖代々受け継がれてきた墓が受難の時を迎えている。墓守が絶えた無縁墓から撤去された墓石は、慰霊の場を離れ、さまよう。人里離れた山中に“墓の墓”が現れ、不法投棄も後を絶たない。   高松市のJR高松駅から車で30分の山中に“墓の墓”がある。約1ヘクタールの空き地にコンクリートで固めた最大幅100メートル、高さ15メートルの扇状の巨大なひな壇が設けられ、壇上に墓石1万基が並ぶ。 「古石材預り所」と称する管理者(52)によると、中四国や関西の寺から撤去された墓石を石材店などの業者が持ち込んでくる。家庭の事情で墓を引き払い不要になった墓石のほか、無縁墓もある。1基1万円で受け入れ、最近は年300基ほど集まる。クレーン機で石を整然と並べ、定期的に雑草をとる。「ここ数年でどんどん増えている。もうけはないが、やめたくてもやめられない」。まだ9万基収容できるという。 一方、不法投棄された“墓の山”もある。兵庫県南あわじ市の山中には推定1500トンの墓石が山積みにされ、山の頂は高さ4メートルに達する。6月半ば、県淡路県民局の職員3人が墓石に合掌しながら現場を見て回った。 「比較的新しい墓もある。墓碑銘から、代々にわたり大切にされてきたんだろうなと思わせる墓もあります」。県民交流室の小塩浩司環境参事は言う。 2008年に廃棄物処理法違反容疑で逮捕・起訴された石材処理業者は、墓石の処分を安く請け負い、破砕などの適正処理をしないまま淡路島に捨てていた。県は撤去するよう指導するが、ほとんど手つかずのままだ。 墓石の不法投棄は昨年も広島県、京都府内で見つかり、ここ5年の間に茨城、千葉、兵庫など各県で業者が逮捕されている。 不要になった墓石は通常、寺や霊園、石材業者が預かるか、処理業者が破砕処分する。だが別の方法をとる業者は少なくない。関東の石材店の社長は「破砕には手間と金がかかる。たたりを恐れて処分しない業者もいる」と話す。 無縁墓はどれほどあるのか。全国的な調査はないが、熊本県人吉市は昨年、全国でもまれな市内の全墓地995カ所の現況調査をした。 人口はこの10年で1割減り3万4500人。65歳以上が32%を占める。「墓が雑草に埋もれている」「墓石が転げ落ちている」。近年増え始めた市民の相談を受け、役場はまる1年かけて、明らかに長く人の手が入っていない墓を拾い出した。 「結果は想像以上でした」。市環境課の隅田節子課長補佐は言う。市内の墓1万5123基の4割超、6474基が無縁墓だった。8割が無縁の墓地もあった。「市として何ができるか。知恵を絞りたい」。妙案はすぐには浮かばない。 |
|
| 第七回 | |
| 「NHKスペシャル,老後破産」を防ぐためには 藤田孝典,NPO法人ほっとプラス代表理事 2014.09.28 | |
NHKスペシャルなどで老人漂流、老後破産が話題になっている。 高齢者の貧困問題だ。生活保護基準以下で暮らす高齢者が大勢いらっしゃることが明らかになっている。わたしの所属するNPO法人ほっとプラスには、生活困窮状態にある人々からの相談が日常的に寄せられている。 当然、65歳以上の高齢者からの相談も多く寄せられる。この背景にあるのは、年金水準の低さや無年金、預貯金の枯渇、医療や介護負担の重荷などさまざまである。   高齢者は基本的に働くことは難しい場合がほとんどである。そのため、収入はこれまでの預貯金や年金、仕送りなどに頼らなければ生活ができない。生活保護受給世帯の45.2%が高齢者である(平成25年7月:厚生労働省・被保護者調査)ことからも理解できるように、高齢期は貧困のリスクが高まる。 そのような高齢者の貧困を防ぐために、先進諸国の社会保障制度は整備されてきた。だから、社会保障制度を活用すれば、一定の改善策はある。しかし、老後破綻と呼ばれる現象の多くは、高齢者が必要な社会保障制度に結びついていないために発生している。 例えば、日本の生活保護制度は、捕捉率が極めて低い。日本弁護士連合会は、生活保護の捕捉率は15.3%~18%しかないと指摘している(日本弁護士連合会生活保護Q&Aパンフレット)。ドイツ64.6%、フランス91.6%と比べても異常な低さだ。捕捉率とは、その制度を受けられる人のうち、どれくらいの人が補足(制度利用)できているかを表す数字である。 だから、日本の高齢者が必要な社会保障制度、特に生活保護制度を利用できていない。生活保護制度が高齢者の貧困に対応できていない、機能不全に陥っているといっても過言ではない。 この利用の低さは、高齢者の生活保護に対する誤解が根強いことも背景にある。 例えば、以下の生活保護に関する噂は誤りである。 ・「年金を受けていると生活保護は受けられない」 ・「持家があると生活保護は受けられない」 ・「車があると生活保護は受けられない」 ・「近くに家族や親族がいる場合は生活保護が受けられない」 ・「仕事をして収入があると生活保護は受けられない」 このような言葉は、私が相談を受けるときに質問されるものだが、どれも生活保護を受けることができる。 生活保護制度は、収入が最低生活費に満たない場合、受給することができる非常にシンプルな制度だ。足りない収入を補う制度だと言える。その足りない分の生活費はいくらなのか、計算方法は【収入が足りない場合に社会手当を受ける方法!~家庭の最低生活費を計算して申請しよう~】を参照いただきたい。 要するに、生活破綻する前に早めに生活保護を利用してほしい。相談窓口はお住まいの役所の福祉課である。 一方で、生活保護に頼らないで生活することが素晴らしいと、美談のように語られてしまうこともある。それは大きな間違いだ。必要な人が社会保障制度を受けずに我慢すると、制度はどんどん弱体化・縮小していく傾向にある。 社会保障制度は、誰もが普通に暮らせるように、あるいは暮らせなくなったときのために用意された人類の叡智といえる。人間だけが持っているとされている社会全体がみんなで支える仕組みである。この機能があるから、私たちは日本という国に住み、みんなで協力しながら経済発展など繁栄を謳歌できている。 そのため、社会保障制度が機能しなくなるということは、国・社会が集団を構成している意味の大半を失うことであるともいえる。 だからこそ、無理せず、多くの高齢者の貧困を改善するために、積極的に生活保護制度を活用していただきたい。 |
|
| 第六回 | |
| 高齢者急増中なのに・・なぜか会員減る老人クラブ 2014.07.03読売新聞 | |
| 高齢者人口が急増する中で、全国の老人クラブの会員数減少が進んでいる。ピーク時から3割弱、約240万人も減少し クラブが担ってきた高齢者の『互助』の機能や地域の安全活動などにも影響が出かねない状況だ。 「団塊の世代」の老人クラブ離れも指摘される中、全国老人クラブ連合会(全老連、東京都)は「100万人会員増強」を目標 に掲げ、今年度から5ヶ年計画で会員獲得に乗り出した。   全老連によると、老人クラブはおおむね60歳以上の高齢者でつくる自主組織。ピーク時の1998年には全国で13万4200 団体、886万人を数えたが、昨年は11万400団体、648万人となり、団体数は18%、会員数は27%も減った。九州・山口・沖縄 の9県でも41万人減の97万人にまで落ち込んでいる。 一方、全国の65歳以上の高齢者人口は昨年、98年の1.5倍以上の3189万人に増加。高齢者が右肩上がりで増える中 会員の減少が止まらない状況だ。 「すでに見守り活動や清掃ボランティアに支障が出ており、焦りを感じている」。福岡市老人クラブ連合会の幹部は危機 感を口にする。定年延長や生活様式の多様化に加え、マンションが立ち並んで住民の交流が少ない地域もあり、勧誘は 容易ではない。 “若手不足も深刻だ” 鹿児島市の老人クラブ「千年千寿会」(約70人)の中野則昭会長(77)は「新規加入が進まず、高齢化が止まらない」と嘆く。 平均年齢は今や80歳に迫る勢い。坂の上にある小学校周辺で下校時の見守り活動を行ってきたが、「坂を上るのがつら い」との声を受け、活動場所を変更したという。 高齢者同士の声掛け、単身世帯の見守りなど相互の生活支援も、老人クラブの重要な取り組みの一つ。孤独死や身元 不明の認知症患者の問題など相次ぐ中、「互助」機能も注目されており、厚生労働省は「各地に根付いた『地域資源』とも いえる老人クラブを活用しない手はない」としている。 ◆老人クラブ⇒戦後、社会福祉協議会の呼びかけで各地に広がった。歩いて集まれる地域で、30~ 100人程度の規模 を標準としている。老人福祉法で福祉増進のための組織と位置付けられ、国や自治体から支援を受けている。 |
|
|
|
|
| 第五回 | |
| 定年後の依存症防ぐ・・飲酒ペース抑えめに 2013.09.27 読売新聞 | |
| 定年退職後に飲酒量が増え、アルコール依存症と診断される高齢者が増えている。酒が強かった人も、加齢とともに肝機能などが衰えるので、酒との付き合い方を改めるなど注意が必要だ。  大阪府高槻市の男性(65)は定年から半年後の60歳の秋、アルコール依存症と診断された経験を持つ。 営業で全国を飛び回るなど「仕事が趣味」だった生活が退職後に一変。「何もすることがなく、無性にむなしくなった」。仕事を持つ妻が出勤するとすぐ、コンビニに酒を買いに行き、妻が帰宅する夜まで飲み続けるように。 ろれつが回らず、妻に注意されても酒がやめられなくなった。ある日、酔って室内で転倒。脳震とうを起こして運ばれた病院で依存症と診断され、断酒会に入って酒をやめた。 アルコール依存症は、健康を損ない、仕事や家庭生活に支障が出ても酒をやめられなくなる精神疾患。 全国の断酒会でつくる「全日本断酒連盟」(東京)の調査(8月末現在)によると、断酒会入会時の年齢別では60代以上の人は23.6%で、10年前に比べ1割近く増えた。50代(31.5%)、40代(29.2%)に次いで多い。 「高齢者が現役時代と同じ感覚で飲んでいたら、依存症になる危険性が格段に高まる」。アルコール依存症治療の専門病院「新生会病院」(大阪府和泉市)院長の和気浩三さんはそう説明する。 シニア世代は肝臓の働きが低下する。体水分も減るため、飲酒すると血中のアルコール濃度が高くなり、少量でも深く酔った状態に陥りやすいという。 和気さんによると、65歳以上の依存症患者の大半が「定年後、昼間から一人で飲むようになった」と話すという。時間の制約や翌日の予定がないための特徴で、大量飲酒につながる危険が大きい。「昼間の飲酒を防ぐには、自治会活動やボランティア活動に参加したり、趣味を楽しんだりして外出の習慣を作ることが大切」と強調する。夜に飲む時も1人酒は避け、家族や友人らと食事をしながらゆっくり飲むようにする。 全日本断酒連盟理事で大阪府断酒会会長の伊藤聡さんは「人によって適量は違うが、週に2日は休肝日を設け、ほろ酔いでやめるのが大切だということをシニア世代は特に意識してほしい。結婚式や同窓会、家族の誕生日など特別な機会以外は飲まない、という自分なりの飲酒ルールを決めておくのも一つの方法です」と話す。 家族の役割も重要だ。高齢者の酒量が増えても、家族が「長年働いてきたのだから、酒ぐらい自由に飲ませてあげたい」ととがめにずにいると、依存症に陥る場合がある。 注意すると、家族に隠れて飲むのも依存症の特徴といい、「本棚など以前は置いていなかった場所に酒を隠したり、ビールの空き缶がこっそり捨てられていたりしたら、早めに保健所や医療機関に相談して」と話している。   高齢者がアルコール依存症にならないためのポイント ・年齢とともに肝機能が落ちているので、現役時代と同じ量、同じペースで飲まない。 ・昼間から飲酒しない。そのためには、社会活動や趣味などを楽しみ、外出する習慣 を持つ。 ・1人で飲まない。歯止めが利かなくなって大量飲酒とならないよう、家族や友人と いっしょに飲む。 ・ほろ酔いでやめる。週2日は休肝日。 ・規則正しい食生活を守る。食事が不要になるのは飲み過ぎ。 |
|
|
|
|
| 第四回 | |
| 実家が汚屋敷に!? 2013.11.19 ダ・ヴィンチ ニュース | |
| 親の家の片付けに悩む人が急増中! なぜ老人の家は片付かないのか? | |
 ..... .....  |
|
『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』(佐藤眞一/光文社) 最近、「親の家の片づけ」に頭を悩ませ、年末年始の帰省が憂うつという人が増えている。未曾有の高齢社会といわれる現代ニッポン。孤独死、独居高齢者、介護など高齢社会の問題は山積みだが、「ゴミ」問題もまた実はこうした高齢者問題のひとつだ。 メディアでも度々取り上げられるが、異常な量のゴミが庭や道路にまで溢れるいわゆる“ゴミ屋敷”が全国に多数存在し、その住人の多くが独居老人だという。「ゴミ屋敷」まではいかなくても「片づけられない老人たち」の問題は年々深刻化しているそう。 足の踏み場もない部屋、汚物も散乱している。そんな高齢の親を見かねて子供や親戚が掃除しようとしても、嫌な顔をされたり、拒否したり──。この現象は男女をも問わないらしい。 しかし一体、老人たちはなぜ「片付けられない」のか。なぜ年をとると「片付けられなくなる」のか。それを『ご老人は謎だらけ 老年行動学が解き明かす』(佐藤眞一/光文社)から読み解いてみよう。 そもそも年をとると、その人が若い頃にはなかったような、さまざまな特徴が見られるようになる。妙にポジティブで有能感を持っていたり、都合のよいことしか憶えていなかったり、人の言うことを聞かなかったり……。そのひとつが孤独感だ。そして、ゴミ問題の根本にもまた“孤独感”があるという。 「人はもともと社会的な存在であり、社会との関わりをまったく持たずに生きていくことはできません(略)ところが何らかの事情で孤立してしまうと、その原因が自分にあったとしても、受け入れられたいという欲求をはねのけられたと感じ、“社会から拒絶された”と思い込み、怒りと孤独感を感じ」てしまうのだという。 さらに孤独感から反社会的行動に走ることも。その代表例がゴミ問題なのだ。きっかけは小さいことが発端だったりするらしい。たとえば「空き瓶や飽き箱を捨てるのがもったいない。ずいぶん前に買ったお菓子だけれど、まだ食べられるから取っておこう」というような。 しかし、若者ならある程度ゴミが溜まるとがんばって捨てようとするが、老人になると体力的に厳しいことも。ゴミの分別も一苦労。挙句に分別されていないので、自分のゴミだけ回収されず、腹立たしく家に持ち帰るが、何が悪いのかもわからない。そんなことが続くと「ゴミを捨てる気力も失せ、“なぜ自分だけ意地悪をされるのか”“誰も助けてくれない”“周りはみんな敵だ”と、孤独感を募らせ、しだいに頑なに、反社会的になっていったとしても不思議ではありません」というわけだ。 こうして徐々にゴミは溜り、近所から苦情が来ても、逆に「いい気味だ」とほくそえんだり、ときに逆ギレしてしまったりすることもあるという。そして、気づけばゴミ屋敷に……という事態にまで至ることも。 こうした老人ゴミ問題に対策はあるのか? 著者が提言するのは「互恵的利他主義コミュニティ」である。これは「誰かを助けます。そして私は別の人に助けてもらいます。だからお返しは結構です」という考えらしい。老人のゴミの分別を誰かがサポートすれば、少しは孤独感も解消され、コミュニケーションも持てる。ゴミ屋敷問題のかなりが解決するだろうと筆者は言うのだ。 確かに理想だが、もうひとつ大きな問題が存在する。それは老人の多くが「人の世話にはなりたくない」と思う「自立神話」である。しかし自立できないからこそ老人へのケアや介護があるわけで、「自立神話」は矛盾したものだ、と筆者は言う。よって自立神話に惑わされることなく「年をとって心身が弱ったのなら、人の世話になっても」よく、「人に上手に依存できるかどうかが、人生の最終章を幸福に送れるかどうかに関わっているのです」と結論付ける。 人間は誰しも老いる。今後も増え続けるであろう高齢者のごみ問題。親や身近にいる老人をゴミ溜めで生活させないためにも、周囲が早期に異変に気付き、プライドを傷つけることなく、さりげなくサポートすることが必要なのかもしれない。 |
|
|
|
|
| 第三回 | |
| 日本薬剤師会会長(児玉孝氏)が決意の告白「患者よ、クスリを捨てなさい」 週刊現代 2014年4月5日号 | |
クスリは毒である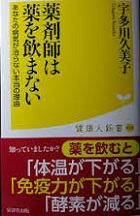  日本人は「クスリ好き」と云われますが、実際、諸外国に比べて日本でのクスリの消費量は多い。昔から日本人には、何か症状が出たら、とりあえずクスリをもらって治そうとする傾向がありました。 なぜ、ここまでクスリ好きになったのか。かなり古くから、土壌があったと思われます。漢方薬の本場である韓国・中国からその知識が入ってきて、緯度や気候も中国と似ていることから、漢方薬に使われる生薬も育ちやすかった。さらに、「富山の薬売り」が全国を回っていたこともあり、一般家庭には置き薬のシステムが定着していました。 そこに輪をかけたのが、1961年から導入された国民皆保険制度でしょう。高齢者の医療費負担がゼロだった時期もあったため、「ただでクスリがもらえるなら、飲んでおいたほうがいい」という雰囲気もあった。病院でクスリを処方されないと不安に感じて、患者さんが自ら「クスリをください」と要求することも増えていきました。 日本で製薬業が発展したことも影響しています。クスリの研究・開発は時間とおカネがかかる知的産業ですから、クスリを作っている国というのは、日本を含めてそれほど多くはありません。クスリが身近に手に入るという面で、日本人は恵まれているのです。 ですが、現代の西洋医学におけるクスリというのは、人工的に作られた化学合成物質ですから、身体の中にはもともと存在しないものであり、「毒」と言ってもいい。できれば飲まないほうが良いものなのです。 人間は高等生物ですから、異物が体内に入ってくれば、それを排除して体調を整えようとして、さまざまな反応を起こします。花粉症なども、まさにその一例です。異物である花粉を排除しようとして、くしゃみや鼻水、涙などの反応が出るのです。これと同じように、クスリも人体にとっては異物であるため、体内に入るとさまざまな防御反応が現れます。 この防御反応が、病気の症状にとって良い作用を起こすと「有効性」となる。逆に悪い作用となって現れるのが「副作用」です。良い働き(有効性)をできるだけ増やして、悪いほうの働き(副作用)をできるだけ抑えるように作られたのが、クスリというわけです。 つまり、副作用はどんなクスリにも必ずあるのです。漢方薬も生薬の中に化学合成物質と同じ有効成分が含まれているからクスリとされるのであって、副作用はある。さらに、必ずしもすべてに当てはまるわけではありませんが、よく効くクスリの多くは副作用のリスクも高いということも知っておいたほうがいいでしょう。 飲んでも病気は治らない  薬局で誰でも買える市販薬より、処方薬のほうが副作用のリスクも高いものが多い。これは「ハイリスク薬」と言いますが、代表的なものに抗がん剤があります。抗がん剤にはがんを叩く強力な効果がありますが、髪が抜けたり味覚を失ったりと副作用も強い。中には毒薬として使われた成分が元になって開発されたものもあるくらいですから、リスクが高いこともお分かりいただけるでしょう。 もうひとつ理解しておくべきことは、「病気を治せないクスリ」もあるということです。風邪薬や高血圧、糖尿病といった生活習慣病のクスリなどが代表的ですが、これらは症状を抑えるものであって、病気を治すクスリではありません。 風邪薬は、熱を下げたり鼻水を止めたり、症状を抑える効果はありますが、風邪そのものを治すわけではない。熱を下げようと思って解熱剤を飲み続ける人もいますが、無理に熱を下げる必要はありません。 発熱しているということは、まさにいま体の中で異物を排除するために防御反応が起こっているということ。その反応を無理に抑えてしまうと、逆に治りが遅くなってしまう可能性もあります。仕事などがあって、どうしても熱を下げないと困るというときにだけ、解熱剤を飲めばいいのです。 また、解熱剤と同様にロキソニンなどの鎮痛剤も、痛みは抑えられても、痛みの原因を取り除けるわけではないですし、長く飲み続ける性格のものではありません。日本では抗生物質の消費量も他国に比べて多いようですが、投与を続けることで耐性ができ、肝心なときに効かなくなってしまうこともあるのです。 超高齢社会の到来に伴って、外科的な処置よりも体に負担が少ない内科的治療を選ぶ人は増え、クスリの消費量はさらに増加していくでしょう。ですが、高齢者はとくにクスリの飲み過ぎに気をつけてほしいと思います。 クスリは体内に入ると、肝臓で解毒・分解されて、腎臓を通って、最終的に尿として体外へ排出されます。この解毒作用は、誰でも歳をとると低下していき、肝臓や腎臓に負担がかかりやすくなるのです。 加齢と共に抵抗力が弱まると、異物に対する反応も弱くなり、副作用が起こっていることにさえ、気づきにくくなってしまう。副作用を自覚できず、さらに深刻な事態に陥ることも考えられます。 治療の方法や副作用の出方は患者さんによってさまざまです。医師は、患者さんに早く良くなってもらいたいという思いでクスリを処方しますが、他のクスリとの飲みあわせや副作用のことを事細かに考えている時間はないはずです。医療が高度化することで、現場の負担はさらに増えていますから。クスリの飲みあわせの管理や細かい副作用についての説明は、薬剤師の仕事になります。 患者さん側も医師から処方されたものを漫然と飲むだけで、何のクスリなのかを理解せずに飲んでいる人が多いのではないでしょうか。 私が実際に経験したケースでは、こんなことがありました。80歳くらいの高齢の男性でしたが、訊くと、26種類ものクスリを処方されていたんです。さすがに驚きました。これほどの量を一度に飲めるわけがありません。なぜ、このようなことになったのかというと、3ヶ所の病院にかかっていたからです。関節の痛みだったり、高血圧だったり、さまざまな症状があって、それぞれの専門科にかかっていたらここまで量が増えてしまった。 そこで、26種類のクスリをリストにしてあげて、病院に相談しに行ってもらいました。医師もびっくりしたようですが、結局、26種類から、たった6種類にまでクスリを減らすことができた。つまり、それ以外の20種類は必要がなかったわけです。その高齢男性は、処方されたクスリを飲みきれなかったので、自分で適当にチョイスして飲んでいました。クスリの飲みあわせによる副作用が出なかったことは幸いですが、本当に必要だったクスリを飲んでいなかったため、何の効果も得られていませんでした。 明らかに飲みすぎです この男性のように、患者さんが自分でクスリの量を調整してしまうことがありますが、これにも注意が必要です。たとえば、一回2錠飲む必要のあるクスリを、一回1錠にすれば半分の効果が出て、一回4錠飲めば効果が倍になるのではと思うが人がいますが、どちらも間違いです。クスリは、ある一定量を飲んではじめて効果が出るので、量が少ないと効果がほとんど得られず、逆に、クスリを2倍量飲んだとき、副作用は時2倍以上になる可能性もあるのです。 26種類というのは明らかに異常ですが、一日に何種類以上のクスリを飲んでいたら飲みすぎになるのかということは一概には言えません。けれど、3ヶ所以上の医療機関から計6種類以上のクスリを処方されて飲んでいる人は、薬剤師に一度チェックしてもらったほうがいいでしょう。それぞれの医師が、患者さんの症状を診て処方しているわけですから、同じ効能のクスリが重なって出されていることがあり得ます。 クスリの重複や飲みあわせによる副作用を防ぐために「お薬手帳」がありますが、それだけでクスリを管理するのは、現実的には限界があるかもしれません。 それに代わる方法としては、「かかりつけ薬局」を持つことも有効です。複数の病院にかかることがあっても、自宅の近くなどにかかりつけの薬局があれば、そこで一括してクスリを処方して管理もしてもらえます。患者さんから「このクスリは効かない」「このクスリを飲むと湿疹が出るから替えてほしい」といった相談があれば、薬剤師は処方した医師に確認する義務(薬剤師法に定められた「疑義照会」というシステム)があるのです。 薬剤師というと、処方箋に従ってクスリを出すだけの専門家という印象が強いかもしれません。ですが、クスリに関することは何でも訊いていただいていいんです。処方薬をもらう際、市販薬やサプリメントなどとの飲みあわせの相談でもいいですし、ご自身の体調のことを気軽に相談できる薬剤師を見つけていただきたい。 クスリ同士だけでなく、サプリメントや健康食品とクスリの飲みあわせで、悪影響が出ることもあります。たとえば、血液をサラサラにするワーファリンというクスリはクロレラのサプリと一緒に飲むと効果が落ちてしまう。こうしたことも、かかりつけの薬剤師に相談できれば、未然に防ぐことができるでしょう。 薬剤師はクスリを売りたがるというイメージがあるのかもしれませんが、それも誤解です。むしろ我々としては、クスリの処方量が減っていくことが望ましい。患者さんの健康を守りながら、最小限のクスリで最大の効果を上げていきたいと思っています。 日本には、昔からクスリが身近なもので、クスリを飲んで病気を治すのが当たり前という感覚が根強くありますが、まずはクスリの正しい知識を身につけ、意識を変えていくことが必要ではないでしょうか。 |
|
|
|
|
| 第二回 | |
| 映画館にも“終活”の波 … 重厚作品に高齢者が熱視線、争奪戦も 2013.12.29 産経新聞 | |
   |
|
| 最近、65歳以上のシニアの方々から「何かいい映画はない?」と尋ねられる。そのたびに私有のDVDライブラリーからお薦めの映画を選んではお貸ししている。たとえば、「ドライビングMissデイジー」「ラヴェンダーの咲く庭で」「木洩れ日の家で」…などなど。いずれも同年代の高齢者が主人公の作品ばかりで、その人生観や暮らしぶりが参考になるらしく、鑑賞後は大概、「面白かったあ」と満足した表情を見せてくれる。 映画館でも高齢の観客を多く見かけるようになった。先日、フランス映画「母の身終(みじま)い」を上映中の「シネスイッチ銀座」(東京都中央区)に足を運んだら、平日にもかかわらず高齢の男女が詰めかけてスクリーンを凝視していた。48歳の息子と暮らすことになった母親の物語で、息子は死期が近い母親が尊厳死を選んだことを知り動揺する。映画館スタッフに話を聞くと「観客の9割はシニア層。映画で描かれた尊厳死についての問い合わせもありますよ」という。映画館のロビーには「終活コーナー」を特設して関連書籍を販売していた。 今やインターネットやスマートフォンなどで気軽に映画が見られる時代。若者の映画館離れが叫ばれて久しいが、一方で劇場に通う高齢者は増えている。その要因について吉祥寺バウスシアター(東京都武蔵野市)の西村協(かなう)支配人は「高齢者には時間やお金があるし、もともと昔から映画館で鑑賞する習慣が身についているからでは」と分析する。また、夫婦のどちらかが50歳以上なら鑑賞料が2人で2000円になる「夫婦50割引」といったサービス制度も浸透しているとみる。 観客の高齢化の影響は映画興行界にも及んでいて、岩波ホール(東京都千代田区)の企画・広報担当、原田健秀さんは「高齢者をターゲットにする動きがミニシアターなどに出てきており、それまで見向きもしなかったシニア向け映画の争奪戦が激化している」と明かす。岩波ホールは早くから高齢化社会を見据えた作品(「安心して老いるために」「森の中の淑女たち」など)を世に送り出してきた。来年2月には105歳のマノエル・ド・オリベイラ監督がジャンヌ・モロー(85)、クラウディア・カルディナーレ(75)、マイケル・ロンズデール(82)といったベテラン俳優を迎えて撮った新作「家族の灯り」を公開する。 岩波ホールの代表作といえば、高齢姉妹の生活ぶりを描いた1988年公開の「八月の鯨」だろう。93歳のリリアン・ギッシュが79歳のベティ・デイビスの妹を演じて話題になった。当時の総支配人、故高野悦子さんは「老人の日常生活と心境を淡々と描くだけの映画は、観客が14、15歳という日本の映画界では敬遠される」(講談社刊「エキプ・ド・シネマPart2」)と危惧していた。だが、ふたを開けてみれば31週間も上映するロングラン。今年2月には創立45周年記念作品として再上映され好評を得た。 「八月の鯨」に出合った高野さんは「一日一日を大切に生きるリリアン・ギッシュに、病気から立ち直った母の姿が二重写しになった。90歳を超えた母が、一日一日をいかに大切に生きているかを私は知っていた。」と述懐している。映画は、自分の人生を見つめ直すきっかけをくれたり、生きていくヒントを与えてくれる。これからも劇場に足を運ぶ高齢者の映画ファンは増えそうだ。 |
|
|
|
|
| 第一回 | |
| 墓じまい、墓守りの後継なく手続き代行業者も登場 2014.03.05 読売新聞 | |
 |
|
| 古里にある先祖代々の墓を撤去し、遺骨を永代供養の合葬墓などに移す「墓じまい」をする人が増えている。少子高齢化の時代になり「墓守りの後継ぎがいない」といった事情があるためだ。 大阪府門真市の男性(66)は昨年5月、兵庫県養父市にあった先祖の墓を撤去した。両親等7人の遺骨は、同府池田市の霊園「北摂池田メモリアルパーク」の合葬墓に移し、納めた。男性は40年前から大阪に住んでいて、養父市の墓へは車で3時間もかかっていた。同居する長女(40)は大阪で生まれ育った。「長女に田舎の墓を守れとは言えず、私の代で墓じまいをしようと思った」と話す。 墓じまいをするには、墓地埋葬法で定められた手続きが必要だ。古い墓の管理者から「埋蔵証明書」を出してもらい、遺骨を移す先の霊園の「受入証明書」などと一緒に自治体に提出し、許可を得た。 先祖が入った合葬墓は、霊園が管理する永代供養墓だ。男性も、将来は妻(65)と一緒に霊園内の「夫婦墓」に入り、十三回忌以降は両親等が眠る合葬墓に移される生前契約をしている。 男性は今回、この霊園を運営する「霊園・墓石のヤシロ」の、墓じまいのサービスを利用した。証明書の提出などの手続きの代行から、古い墓の撤去、合葬墓で遺骨を永代供養する費用などまで含め、遺骨2人分で29万8000円(税抜き)。追加料金は一人分5万円(同)。墓の規模や移動距離によっても変わってくる。 同様のサービスを提供する業者は増えている。「やすらか庵」(千葉)は、墓の撤去後、遺骨を東京湾や千葉県内の森林へ散骨するサービスをしている。霊園・寺院との交渉から改葬許可の手続きや遺骨を取り出す際の供養までを僧侶の清野勉代表(54)が行う。数年前から「先祖の骨を先に散骨して墓を閉じたい」という要望が増え、昨年10月から墓じまいの支援を開始した。2月までに5家族が墓を撤去し、相談も30件以上寄せられた。 「清蓮」(横浜市)は散骨を契約した客が墓じまいも希望する場合、手続き方法などをアドバイスする。11~13年で約400基の墓が撤去されたという。 トラブル防ぐ事前相談 「墓じまい」をしようとしたところ、檀家が減るのを防ぎたい寺院から高額の金銭を要求されるケースもあるという。また、親族が先祖の墓をなくすことに反対してトラブルになることもある。墓じまいを円満に進めるためには、寺や親類への早めの相談、報告が欠かせない。 檀家が減って運営が苦しい寺も少なくない。ただ、寺離れが進んだり墓守がいなくなったりして墓地の管理料すら納めてもらえなくても、無縁墓にしてはいけないとお勤めを続けている住職も多い。 葬儀コンサルティング業務の吉川さんは、「後継ぎがいないといった事情を説明し、途中経過を報告するなどこまめな連絡を心がけてほしい。離檀料(りだんりょう)は1回の法要で寺に支払う金額が目安。実際には数万円~20万円程度が多いようです」と助言する。 |
|